関係者各位
いつも大変お世話になっております。
元道庁職員の鈴木邪道でございます。
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
配属と業務の概観
最初に、入庁からの配属経歴について説明します。
なお、具体的な部署名については、ぼかして書かせていただきます。
配属と業務のリアル
入庁1年目 本庁〇〇部〇〇課〇〇係
入庁初年の4月私が配属された係は部内の調整事項全体を取りまとめる “庶務の何でも屋”といったところでした。
各部各課からの照会対応、部内職員の福利厚生、さらには議会対応…。
入庁1年目で経験するにしては色々情報が入り過ぎるところにいたような気もしますが、それゆえに「行政の現場を支える裏方業務だ」と前向きに捉え仕事に取り組んでいました。
ところが実際は、無駄に多い謎の手続きの連続。
回ってくる決裁文書のほとんどは「何のために必要なのか」「そんなこといちいち上司に聞く必要があるのか」もわからない。
とにかく形式を満たすことが目的になっていました。
この時点で、役所で働く人たちの仕事の仕方は「言い訳づくり」(要はアリバイ作り)が基本だということを理解しました。
入庁2年目 同じ課の◇◇係へ配置換え
翌年には◇◇係へ異動しました。〇〇部のいくつかの課の予算や北海道開発予算の要望を担当しました。
ここでの1年が私の短い公務員人生にとってのある意味転機となるような経験でした。
4月の決算対応
年度替わりでのいきなりの決算対応。連日終電近くまでの残業。
明許繰越、事故繰越、戻入…
そりゃあ言葉で聞いたことはありますよ。でも、入庁2年目で予算業務初めての人間にいきなり何十億というお金の管理させますか?
最終的な決裁や責任は係、課、部が負うとしても、実務経験のない人間にいきなり担わせるという構図に、この組織の人を育てる体制の不在を感じました。
6月の北海道開発予算の要望
要望段階での増額要求を絶対に認めようとしない財政課と、実現可能性や事業の効果を無視してとにかく自分たちの都合だけを並べて予算獲得を要求してくる関係課の板挟みで心が壊れそうな日々が続きました。
最終的にはあれだけ抵抗していたにもかかわらずHG(〇谷〇岳参議院議員)案件だからということで、すんなりと査定を通る「じゃあ今までのやり取りは何だったの」感。
11月~年末からの予算要求
「去年と同じ手順で数字を入れ替える作業」で何故こんなにボロボロにならないといけないのか。そもそも道民のための施策を積み上げていくのが予算なのに、それを一律で10%、15%カットする結論ありきで話を進めていく財政部局への不信感が収まりませんでした。
入庁3年目 再び〇〇係へ
心身の限界を迎えた私は、1年で元の〇〇係へと戻されました。
ちなみに、課内での配置転換は所属長(課長)の所掌事項となっており、課や本庁-振興局間の異動とは別の扱いとなっています。
1年空いたとはいえ、一度経験した仕事や流れが多く、任された業務量は新卒時代よりも増えましたが、この時期はかなり心に余裕を持って働けていました。
年度の後半からは、当時流行していたDX関連事業ということで、課のレイアウト変更というこれまで誰も手掛けたことのない取り組みを行ったり、DX推進関係の事務費を獲得するために総務部と予算折衝したり、事務機器卸業者のショールームを見学に外勤したりと比較的のびのびと過ごせた1年間でした。
入庁4年目 □□振興局□□課□□係
入庁4年目にして初めての地方勤務となりました。 ここでは、主に防災の業務を担当することとなりました。
防災といえば命に関わる重要な仕事だと思うかもしれません。
しかし、実態は、市町村と国の間でメールや電話内容を転送する“伝書鳩係”。現場を動かすことも、判断する権限もありません。
それでも警報が鳴れば15分以内に庁舎に出なければいけません。夜中だろうが休日だろうが呼び出されます。そのこと自体は、大変ながらも与えられた役目としては当たり前のことだとは思います。
しかし、出てきたところで何か出来るわけでもない。数十分に一度、市町村や警察署に電話してそれを記録する。現場で実際に対応・情報収集している市町村や警察署にとっては迷惑この上ない道庁からの電話。
そして、担当者不在等で情報収集が出来なければ、上司や係長から「報告書が書けないぞ!どうするんだ!」と詰められる。
この組織の存在意義を決定的に見失った瞬間でした。
入庁4年目の冬、私は退職しました。
以上が、私の道職員時代の簡単な経歴とその時感じたことです。
北海道庁の“リアル”な文化
既にお腹いっぱいかもしれませんが、以下では、北海道庁内に根付くリアルな文化について、いくつか紹介します。
議会答弁マニュアルに「明言を避けよ」
入庁して3か月程経ち、議会(2定)が始まったときのことです。道民の代表である議員の質問に対し、答弁マニュアルの太字で強調されていた一文がこれです。 つまり「何も断言しないのが安全」という発想が染み付いています。
当時、初当選したばかりの鈴木直道知事は、道議会で長年問題となっている「答弁調整」について、今後は行わないとの発言をしていました。
しかし、実際は知事がどうこう以前に、末端の役人レベルで責任回避の文化がマニュアル化されていたんですね。
ちなみに、今では知事もすっかり答弁調整を活用しています。
会議は演劇
部内の会議であっても台本が先にあって、出席者は台詞を読むだけ。結論と発言が事前にそろえられた会議で、議論するふりをしているだけなんですね。
終わった後はボイスレコーダーから音声を手作業で文字起こし。
非効率・無意味の極みです。
情報の秘匿と縄張り主義
「〇〇部」「総務部」「財政局」…。
同じ庁舎にいながら他部署は敵扱い。
「この予算は財政に知られると削減されるから絶対に話すな」「総務課に情報が漏れたら説明が出来なくなる」など、情報は常に囲い込まれていました。
「お前は財政課の人間かよ」
これ、私が実際に同じ部の事業担当の方に言われた言葉です。「道庁職員」ではなく、「〇〇部職員」「財政課職員」と言ったアイデンティティが優先で、組織としての一体感や市民志向は皆無に等しいのが実態です。
言動に滲み出る“人”の問題
入庁当初は「広域行政の役割」「地域に寄り添う政策」という大義に共感していました。
しかし、現場で見た光景は期待とは全く乖離していました。
それは、組織文化だけでなく、“人”にも現れていました。
あらかじめことわっておきますが、こうした人たちは職員の全てではないです。
ただ、業務遂行能力が高く出世を重ねていくような職員でもこのような人が割と普通にいて、若年者や真面目に頑張っている職員を潰しているというのも、また事実であるということは理解してほしいです。
事なかれ主義の極地
所掌事務分担表に書いていないことは、コピー用紙の補充ですら「担当外」。
問題が起きても「自分の担当外なので」で済まされる事なかれ主義が徹底していました。
“定年まで逃げ切れればOK”が暗黙の目標
昇進して責任が増えるより、昇進拒否・異動拒否してぬるく過ごすことが賢いとされていました。しかもこれ、50代後半くらいになって出世を諦めた職員が言うのではなくて、入庁して数年の若手職員も同じことを言っているんです。
高卒だと20歳とか21歳、大卒でも25、26歳の職員が「一生主任で良い。係長昇進の話が来たら拒否する。評価最低で良いから一生札幌からの異動を拒否する」と言っているんですね。
たまにやる気のある若手がいて挑戦的なことを言おうものなら、
「あなたが偉くなったらやると良いよ」
「少なくとも俺がいるうちは無理だ。来年課長が替わったらまた言ってくれ」
と冷笑されます。
北海道内の地理も知らない職員
自治体や地域に興味を持っている人が多いと思っていたのですが、地域の地理や行政の取り組みを知らない職員も少なくないです。
「留萌って道東?」
という言葉を耳にした時は腰を抜かすかと思いました。
不健康な職場文化
公務員=品行方正のイメージとは裏腹に酒・タバコ・不倫・風俗の話が“飲み会や雑談のネタ”。
倫理観の欠片もない会話で盛り上がる一部の職員。
コンプライアンスの概念が30年遅れていると感じました。
国への完全従属体質
議会答弁、予算編成、何かあれば「国の指針がまだ出ていない」「国にお願いしていく」。
そこに道としての自主性などはありません。
「機関委任事務が廃止され、自治事務となったことで、自治体の自主性は上がりました」
なんていう公務員試験で良く出てくるセンテンスなんて全く実態を表していません。
実態は“国の出先機関”のままです。
財政破綻した夕張市の自治が制限されている様子を「箸の上げ下げまで総務省に指示される」と表現した方がいますが、北海道庁の場合はそれを笑えないどころか、「箸の上げ下げまで国の方針を待つ」状態。
むしろ自分たちの方がよほど国に依存していると言えるでしょう。
辞めた後に見えたもの
まあそんなこんなで、私は入庁4年目の冬に道庁を退職するわけですが、その際も1つエピソードがありました。
退職願を出した時、当時の上司たちは私にこう言いました。
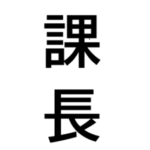
法律上、退職は予定日の2週間前で良いとはあるけれどさぁ…
再来週から有休入るだなんて、もう少し前に言ってくれれば…
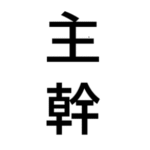
提出してくれた退職の書類だけれど、正式な様式というものがあってこちらに書かれていないものは正式な文書としては扱えません。
改めて書いてください。
最後の最後まで、“規則”や“手続き上のスケジュール感”しか見ていなかったんですね。
私という人間の心情や組織の問題点というところには全く興味がないんだな、と。
ここまでくると、怒りよりも「この人たちに自分は何を熱くなっていたんだろう。何を期待していたんだろう」という諦めの気持ちが出てきました。
私の場合、道庁での仕事を続けながら転職活動をしていました。
約2か月転職活動をして内定を数社獲得。
最終的に札幌に支店を構える東京本社のリサーチ・シンクタンク系の民間企業への入社を決めました。
この会社では道庁時代よりも給料が約2割上がり、「地方公務員は替えが効かないから転職なんて無理」という思い込みを克服することが出来ました。
また、「自分の人生は自分で切り拓く」「人生の主導権は常に自分で握っていなくちゃいけない」というマインドを取り戻せたのも、公務員を辞めて良かったことです。良い意味での「転職癖」が付いたように思います。
これは体調を崩しても一つの職場にしがみついているままでは絶対に得られない価値観、体験だと思います。組織に依存しない価値観や働き方の選択肢が開けたと思います。
今、振り返って思うこと
「あの時、あのタイミングで辞めて良かった。」
一言で言えば、それに尽きます。
私にとって 「退職=逃げ」ではなく、「退職=自分の人生を取り戻す手段」でした。
公務員から民間へ転職し、年収も上がりました。
何より、“自分の判断で動ける”という当たり前の自由を取り戻せました。
もしあの時、他の大多数の同期と同じように何やってるのか分からないような緩い部署に配属され、のんびりした最初の3年間を過ごしていたら、 もしかしたら今も道庁にいたかもしれない。
でも、そんな“たまたまマシな職場”に当たる運任せの人生、いわば“配属ガチャ”で自分の社会人人生を決めるなんて、私はもう御免です。
行政組織の最大の問題点
ここまで、私の個人レベルの経験から、公務員時代に辛かったこと、嫌だと思ったこと、組織の問題点などを書いてきました。少しだけ、日本の地方行政組織の構造的な問題点についても触れましょう。
北海道庁に限らず、日本の地方行政全体に共通する病巣は、首長ですら責任を取ろうとしない「責任からの逃避」と、最後は国の言うとおりにすれば良いと考えている「思考停止」だと考えます。
この点については、今後も当ブログにて分析、解説をしていきます、
公務員制度そのものが悪いわけではありません。
問題は、制度を運用する側が「制度のために人間がいる」と思っていることです。
本来は逆なんです。人間が制度を使って、社会をより良くするためにあるはずです。
北海道庁はその順序が完全に逆転していた。
だからこそ、あの職場を離れてようやく私は、“人間らしく生きる”という感覚を取り戻せました。
このブログを愚痴の掃きだめで終わらせないために
この記事を読んで、「そこまで言う必要ある?」と思う人もいるかもしれません。
また、「所詮は辞めた人間がぐちぐち言ってるだけだろ?」と思う人もたくさんいるかと思います。
確かに、道庁で幸せを感じながら働いている方もいるでしょう。夢と希望を持って就職したい方もいるでしょう。自己実現をしながら働いている方もいるでしょう。
辞めた人間が今更ブログで組織の問題点を書き連ねているのはダサく見えるかもしれません。
でも、実際に現場を知る者として、黙って見過ごすことはできませんでした。
退職から数年、当時の記憶や感情が薄れていく中でも、たまに烈火の如くあの日々を思い出すことがあるんです。それはトラウマのフラッシュバックではありません。
「あの時は大変だったけど、今では良い思い出だよ」
で終わらせたくないという私自身の心の声です。
道庁は、北海道の未来を背負うべき行政機関だ。 だからこそ、今のままではいけない。
私はもう職員ではないけれど、外から見守る者として、あの組織に「変われ」と言い続けたい。
だから私は、このブログを書こうと思いました。
以上、北海道庁を辞めた経緯についてお知らせいたしました。
何卒よろしくお願い申し上げます。
令和7(2025)年11月11日
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道庁生存戦略部
異端企画局
内部是正推進課非公式記録整理係
主事 鈴木邪道
ーーーーーーーーーーーーーーーーー



コメント
初めまして。私は定年となった元道職員です。 鈴木 邪道さんが4年間で経験された道庁組織について
冷静な分析と提言をされていることに感心しました。
>>道庁は、北海道の未来を背負うべき行政機関だ。 だからこそ、今のままではいけない。
私も、鈴木 邪道さんと同様に、多少は愚痴を含めてNOTEで情報発信していますので、手が空いたときにでもご訪問ください。
コメントありがとうございます。
もう1つのコメントも読ませていただきました。
定年まで道庁で勤め上げられた方からこのようなお言葉をいただき、大変励みになります。
ご指摘の「変えようとすると必ず反対する人間がいる」
という点、まさに私自身が最も強く感じた部分です。
また、事務の進め方やアプローチを変えるだけで、長年停滞していた案件が短期間で片付くというご経験談は、現場を知る者でなければ書けない、非常に示唆に富むお話だと思いました。
私自身は在職期間も短く、見えていない部分も多いと思っていますが、
「工夫しないことが常態化してしまっている組織文化」
については、世代を超えて共通する課題なのだと改めて感じましたし、たかが4年といえど、それなりの修羅場を経験した自負と、毎日毎日悩み考えて仕事をしてきた自覚ゆえ、自分の経験談を書いて行こうと決めた次第です。
実はnote、自身でブログを始める前後に発見しておりまして読ませていただいております(*^_^*)
同じ立場を経験した者同士として、今後もこうした議論ができれば幸いです。
引き続きよろしくお願いいたします。